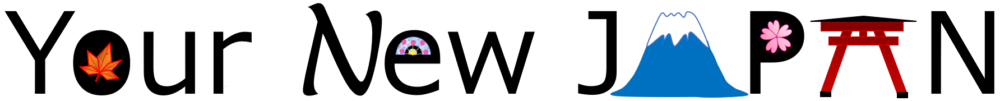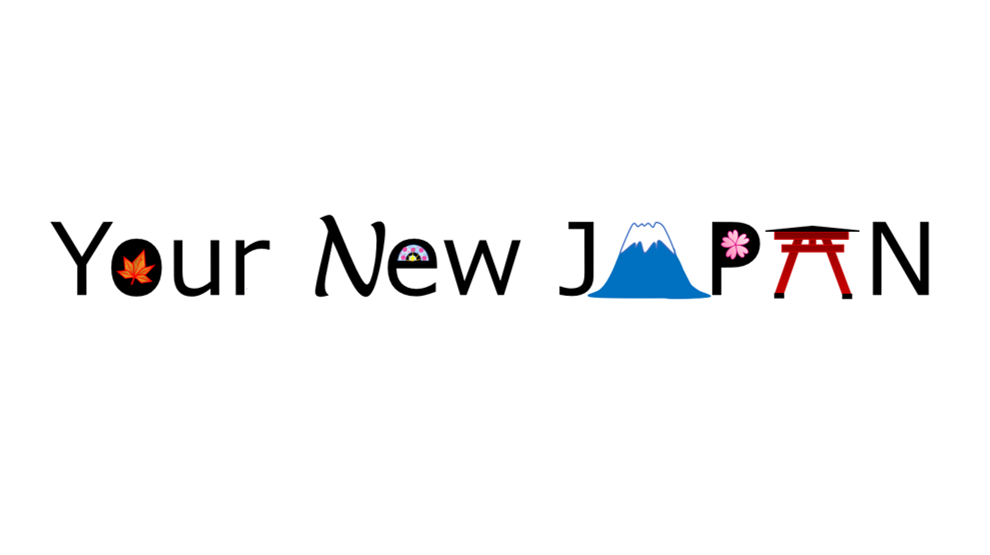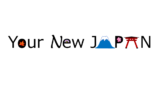日本で日常的に使用される日本語の文字には、ひらがな、カタカナ、漢字があります。その他にもアラビア数字(1、2、3、・・・)、アルファベット(a、b、c、・・・)、ローマ数字(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、・・・)が使用されます。
日本語の文字は非常に多く、日本語を学習することが難しい理由の一つです。
特に漢字の数は多く、全ての漢字を覚えることは、日本人でも不可能です。
このページではひらがな、カタカナ、一部の漢字を学習することができます。
ひらがな
ひらがなは、日本語の基本的な文字の一つです。
種類は清音、濁音、半濁音、拗音、撥音、促音、長音に分かれます。
清音は「あ」「い」「う」などの基本形で、日本語の単語の多くを構成します。
濁音は「が」「ぎ」「ぐ」等、半濁音は「ぱ」「ぴ」「ぷ」等で、文字に「 ゛」や「 ゜」を付けて発音を変え、拗音は「きゃ」「きゅ」「きょ」等で小さな「ゃ」「ゅ」「ょ」で音を変化させます。
撥音は「ん」のみで、単語の頭に来ず、促音は「っ」のみで、短く詰まった音を表します。長音は「ー」のみで、前の文字の音を伸ばします。
ひらがなは一文字では意味を持たず、複数のひらがなを組み合わせることで意味のある単語ができます。
▼▼ひらがなの一覧はこちら▼▼
カタカナ
カタカナは、ひらがなと同様に日本語の基本的な文字の一つで、文章や会話、特に外来語や外国語の表記に欠かせません。
種類は清音、濁音、半濁音、拗音、撥音、促音、長音、外国語の発音を表現するカタカナの8つに分かれます。
清音は「ア」「イ」「ウ」などの基本形で、日本語のカタカナ単語の大部分を構成します。
濁音は「ガ」「ギ」「グ」など、半濁音は「パ」「ピ」「プ」などが含まれ、文字に「 ゛」や「 ゜」を付けて発音を変え、拗音は「キャ」「キュ」「キョ」などが含まれ、小さな「ャ」「ュ」「ョ」を伴います。
撥音は「ン」のみで単語の頭に来ず、促音は「ッ」のみで短く詰まった音を表し、長音は「ー」のみで前の文字の音を伸ばします。
外国語の発音を表現するカタカナは「ウィ」「ウェ」「ウォ」などがあり、外国語の音に近い発音を示すことができます。
カタカナもひらがなと同様に一文字では意味を持たず、複数を組み合わせて初めて意味のある単語が形成されます。
▼▼カタカナの一覧はこちら▼▼
漢字
漢字は、ひらがなやカタカナと同様に日本語を構成する重要な文字のひとつで、ひらがなやカタカナと異なり、一文字ごとに意味を持つ点が大きな特徴です。
例えば「一」の漢字は何かが1つあることを表し、「日」の漢字は太陽や日付の意味を表します。このように、漢字は単なる音だけでなく、概念や事物を直接的に示す役割を果たしています。
日本語の文章において、ひらがなやカタカナだけで書かれた文章は読みにくく、意味もあいまいになりがちです。そこで、文章を読みやすくし、意味を正確に伝えるために漢字が欠かせません。
漢字の総数は諸説ありますが、10万字を超えるとも言われています。しかし、日常生活で用いられるのはそのごく一部に限られています。
日本の小学校では約1,000字を段階的に学びます。本や新聞を読むために習得が必要な文字は「常用漢字」と呼ばれ、およそ2,000字あります。
漢字を理解することは、日本語を深く学ぶ上で非常に大切であり、豊かな表現や正確な理解に欠かせません。
▼▼常用漢字の一覧はこちら▼▼